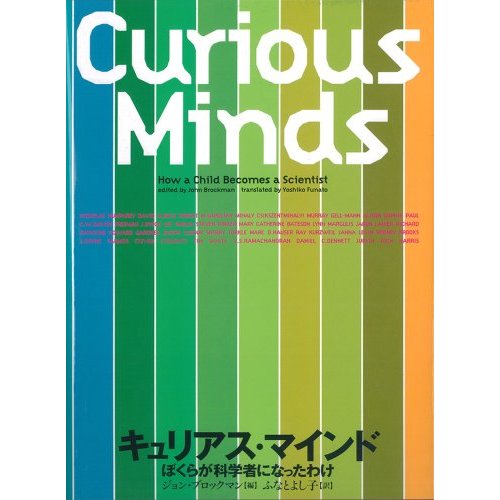
「好奇心」、それは「てら子屋」が大切にしているものだ。そのものずばり、タイトルとなった本の邦訳版が先月発刊された。売り文句は、「科学者になりたい子どもと、科学者になりたかった大人へ、『13歳のハローワーク』の幻冬舎がおくる」という具合。商売柄、知らんぷりもできず、忙しい年度末だというのに読んでしまった。27名の超一流科学者が綴るエッセーの筆致は様々で、おもしろい話しもかなりあった。
しかし、みごとに私が関心を向けている人たちが並んでいる。楽しみや創造性をテーマにした心理学者のチクセント・ミハイ、言語学のピンカーも、利己的遺伝子のドーキンスも、人類学のティム・ホワイトも、掃除ロボットのルンバを開発したコンピュータ・サイエンスのロドニー・ブルックスも、脳科学のジョゼフ・ルドゥーもいる。それだけで、わくわくしてくる。読み始めると、止まらなくなる。意外な展開や、研究業績と生い立ちのギャップ、着想の出発点に関わる多くの話はおもしろい。
人工知能のブルックスの出発点は、家の車庫を新しく作り、車庫代わりだった小屋がブルックスら兄弟の専用の工作場になったことから始まっている。やっぱり"物置小屋"だ!そこで手製のゲームマシンを作り始め、脳の構造を目指していったという。大学入学までに購入したICの数は7400個というからスゴイ。
ドーキンスは、意外にも外に出かけているより、家の中で本を読みふける幼少時代を過ごしている。そして、ドリトル先生シリーズを何度も読み返しているうちに動物学者への道を知らぬ間に歩み出している。そして、彼の科学者としての成長は、持てる生来の才能というよりも、場やチャンスやアドバイスを傍らから供してくれた多くの師のおかげを力説していた。
一方、ピンカーは、この手の(偉大な成功者たちの)話は、消費者を惑わすシリアルの箱の裏の写真やイラストと同様に、ごまかしや間違いがつきものだから気をつけろと、人間の記憶の怪しさを指摘しつつ、皮肉っぽく始めている。そして、遺伝子と偶然のおかげで生まれつき科学の道に必要不可欠な才能と気質に恵まれている人たちが、得るべくしてよい環境を得て、気が付けばそういう道にいるのだと述べている。身も蓋もないかもしれないが、実験心理学者の彼でこそ言えることかもしれない。
こうして読み通してみると、優れた科学者達は、必ずしも子ども時代に科学者になろうという明確な目標をもったわけではない。しかし、それぞれ将来への発火点を持っていることに気づく。また、多くの人たちは、そういう発火点となりそうな場面に接するチャンスに恵まれていることも確かだった。「てら子屋」も、そういう発火点のチャンスの場でありたい。着火するかどうかは人それぞれで構わない。しかし、チャンスは多いにこしたことはない。多くの科学者たちは、自分の興味に素直に生きてきた結果、今がある。改めて、そうだよなあと思う。小中学生が、職業図鑑のごとき本を与えられて、「さあ、選べ。さあ、どの仕事だ!」と迫られるのは、やっぱり変だ。その時々、その場面場面に、自分に素直に周囲の刺激を受け取って育っていくのが最高だと確信できた。
自分の子どもの話題になるが、先日、今学年最後の化学実験で使った先生のプリントというものを見て、「すごく、いいなあ、素晴らしい先生だな」と、うれしくなった。テーマは「酸化・還元反応&炭酸飲料を作ろう」だ。中身を見ると、派手な反応の「テルミット反応」がある。先生の演示実験だが、こりゃ凄そうだ。先生は、反応させる直前に生徒たちに、ケイタイで写してもいいと言ったそうで、みんな一斉にケイタイのカメラをビーカーに向けて固唾をのんだらしい。そして、激しく燃えあがる様子にみな感激というわけだ。もちろん、私もその動画を見せてもらった。とやかく言われている、子どもたちのケイタイだが、そういう使い方は大いにありだろう。そして、その日の最後の実験がふるっている。炭酸水素ナトリウムとクエン酸を反応させてレモン水を入れて炭酸飲料をつくるというのだ。その実験の目的を、先生は「一年間のお互いの感謝を込めてありがたく炭酸飲料でのどを潤す」とプリントに記していた。素晴らしい。息子が作ったものは、レモン水の入れすぎでかなり酸っぱかったらしい。こんな授業を私も受けたかった。
その学校の校長先生が、保護者向けの広報誌上で、教育の「再生」とは、教育がすでに死に絶えたとでも言いたげな傲慢な物言いではないかと、巷の無責任な教育議論に対する憤りを訴えていらっしゃった。生徒や教師によって日々織り成される豊かな現場からの、自由な発想によってこそ教育は営まれると主張されていた。「好奇心」は、そういう現場からこそ生まれるのだと信じる私は、清々しくスカッと爽やかな気分になった。まだまだ世の中、捨てたもんじゃない。



